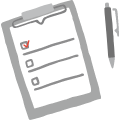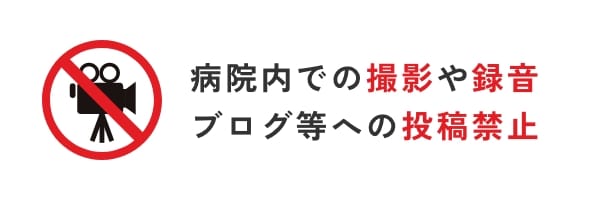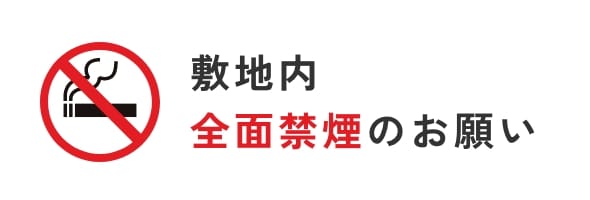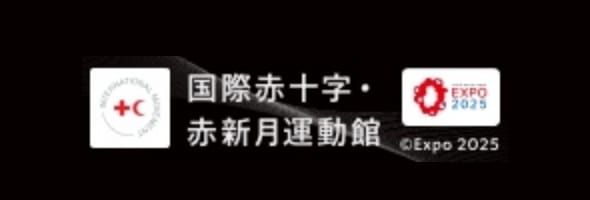放射線科
医療技術部
放射線科のご紹介
放射線科部の技術部門では、エックス線を使う一般撮影・CT・TV・IVR、磁器を使うMRI、超音波を使用する超音波検査、放射線を使用する放射線治療の業務を行っております。救急体制にも対応しており、検査・治療の補助を迅速にできるように目指しております。
診療内容・特色
一般撮影

一般撮影とは、X線によって胸部撮影、腹部撮影、関節・骨の撮影(関節の状態、骨折などの診断)をするものです。
一般撮影(X線単純撮影)には、FPD(flat panel detector)搭載撮影装置を使用し、高精細画像の提供と低被ばく線量での撮影が可能となり、撮影後、瞬時に画像の確認をすることが可能です。また、全脊椎撮影や下肢全長撮影などが一度に撮影でき診断に有用な画像が提供できます。
画像はデジタルデータとして画像サーバーに保存され、各診察室や病棟のモニターで閲覧可能なシステムが構築されています。また、他院紹介用の画像もデジタル化されており、写真の劣化の心配がありません。
病室での撮影も行っておりポータブル撮影と言います。ベッド上安静が必要な患者さんには、病室での撮影を行っております。
手術室での撮影:専用の移動型透視装置(3D対応)があります。また、撮影には専用のポータブルX線撮影装置があります。
歯科系撮影:デンタル撮影、全歯列を断層撮影するパノラマ撮影、セファロ撮影(頭部規格撮影)を行い歯科矯正治療にも対応しています。
骨密度測定:骨塩定量とは骨塩の密度をはかることで、骨粗しょう症や代謝性骨疾患の診断に用います。
CT

SISIEMENS社製 SOMATOM DefinitionAS+
(0.6×128列マルチスライスCT)
Canom社製 Aquilion ONE INSIGHT Edition
(0.5×320列 エリアディテクタ)
CTとはComputed Tomography(コンピュータ断層撮影)の略です。X線を発する管球とX線検出器がドーナツ状の架台内を回転しながらデータ収集し人体の輪切り画像をコンピュータによって再構成する装置です。この装置に寝た状態でCT検査を行います。近年の技術進歩により、広い範囲をより早く、より詳細なCT検査が可能となりました。当院では画像データからカラーの3次元画像等を作成し、詳細な診断情報を提供しています。
日本ではCT保有台数が多いとされていますが、被ばくと画質の調整を常に監視し高画質と患者さんの被ばく線量低減を両立させています。
造影剤という薬品を腕の静脈から注入した検査も行い質の高い検査ができています。また、24時間の救急体制も行っており外傷などの緊急時にも貢献しております。CTで行う治療の手技にも活躍しております。2台のCTに4人の診療放射線技師が携わっております。
X線テレビ

X線を使って体の中の臓器の様子をテレビ画面でリアルタイムに観察しながら検査や治療を行います。造影剤を用いた検査の種類としては、バリウム、ガストログラフィン、空気、ヨード系造影剤、非ヨード系造影剤があります。検査の手技により口から飲んだり、注射器で注入します。
主な検査として、
胃透視検査:バリウム(造影剤)と胃を膨らませる発泡剤を飲んでいただき、胃の壁にバリウムを付着させ、充満像、二重造影像などを撮影する事により、胃食道の形態、細かい胃壁の凹凸を詳しく観察することで潰瘍、早期がんを見つける検査です。
注腸検査:バリウム(造影剤)や空気を肛門から逆行性に注入し、直腸~S状結腸~下行結腸~横行結腸~上行結腸~回盲部まで撮影していきます。この検査も胃の検査同様、大腸の粘膜にバリウムを付着させ、隆起性病変、潰瘍、ポリープ、がんを見つける検査です。
尿路造影:静脈注射、点滴、尿管カテーテル法により造影剤を注入します。腎盂、尿管、膀胱を造影し結石、狭窄、腫瘍の有無などの検査をします。
膀胱、尿道造影:カテーテルを尿道に挿入し逆行的に造影します。膀胱内の器質的病変、排尿異常、尿道病変、前立腺病変の検査をします。
脊髄腔造影:脊髄腔に造影剤を注入し脊髄、神経根の状態を検査します。椎間板ヘルニア、神経根ブロック等の検査、治療を行います。
関節腔造影:四肢の関節腔に造影剤を注入し、外傷や脱臼による関節嚢、靭帯などの損傷、変形関節症などの検査をします。
嚥下造影検査:飲み込みができない人や、誤飲(食べ物や水分を飲み込んだ時によくむせる)をする人などを対象に、造影剤入りの嚥下食(2~6種類)を食べていただき、透視下でその嚥下食の流れや経過などをみる検査です。
透視下内視鏡:口や鼻から体内にアプローチする内視鏡とX線透視撮影システムを併用することで、開腹手術のように被検者の身体に大きな負担をかけることなく、低侵襲で検査・治療を行えます。
血管造影・IVR(interventional radiology)

IVRとは、医療場面で活躍の場を広げている治療法で、正確には「Interventional Radiology=インターベンショナルラジオロジー」、日本語では「画像下治療」と訳されています。文字通り、X線(レントゲン)やCT、超音波などの画像診断装置で体の中を透かして見ながら、細い医療器具(カテーテルや針)を入れて、標的となる病気の治療を行っていきます。代表的なIVRとしては心筋梗塞の治療、脳の血管内治療、また肝臓がんなど臓器のがん治療などがあります。
血管の中から行う手術、というとわかりやすいかもしれません。
IVRは、外科手術のようにお腹や胸を切らずに、体の奥にある臓器や血管の治療ができる方法です。そのため、患者さんの体への負担が圧倒的に少ないという特徴を持っています。またIVRは治療できる範囲や対象の病気が大変多いのも特徴です。私たちの体の中には10万キロに及ぶ血管と多くの管(消化管や尿管など)が張り巡らされていますが、IVRではこの血管や管の“迷路”を体の外から観察しながら、カテーテル(血管の中を通すチューブ)や針を走らせ、目標である病気の元に正確にたどり着けるからです。このため、体の負担は小さくても、IVRで対応できる病気は多いのです。当院では24時間救急に対応しておりIVRを実施可能です。
MMG
マンモグラフィは、乳房専用のX線装置を使って撮影するので、乳房内の微細な変化を捉えることができ、視触診だけでは発見しにくい小さな腫瘤や石灰化を見つけることができるため、早期の乳がんの発見率を高める大変有益な検査です。
乳房は柔らかい組織でできていて立体的で厚みがあるので、そのままの状態で撮影してしまうと乳房全体が写りません。また、乳房の中の乳腺や脂肪、血管などが重なってしまい、もし病変があったとしても隠れてしまうことがあります。よって、放射線技師が直接乳房に触れて引っ張るように広げ、圧迫板というプラスチックの板で圧迫していきます。痛みを伴う検査ですが、こうすることで乳腺腫瘍や微細石灰化の描出が可能になり、放射線による被ばくを少なくする効果もあります。緊張しているとうまく伸ばせず、逆に痛みを増強してしまうことがありますので、リラックスして検査に臨んでください。そのつど患者さんと痛みを相談しながら検査を進めていきます。より良い写真を得るためにどうぞご協力をお願いします。
当院でのマンモグラフィ検査について:精度の高い画像を提供するため、装置の日常管理も実施し、日本医学放射線学会の定める使用基準に適合した専用の装置を使用しております。なお、当院は、日本乳がん検診制度管理中央機構のマンモグラフィ検診施設画像認定施設を取得しています。また、当院は女性の診療放射線技師が在籍しており、全てのマンモグラフィ検査を女性技師のみで対応しています。撮影に関して気になることがあれば遠慮なくおたずねください。
超音波検査
超音波を物質にあてて、反射した情報を画像にします。体への害や痛みがないため、検査を繰り返し行うことができます。超音波とは、人が聴くことができない高い周波数の音波です。超音波を英語でecho(エコー)というので、超音波検査をエコー検査とも言います。体にゼリー状の物を塗って行います。当院で行っている超音波検査は、腹部超音波検査・甲状腺超音波検査・乳腺超音波検査・頸動脈超音波検査・下肢血管超音波検査・体表超音波検査・心臓超音波検査などを中心に行っております。
MRI

MRIは磁力と電波を使って体内の状態を描写する検査で特有の画質が得られる検査です。X線撮影(レントゲン撮影)やCTのように放射線ではないため被ばくはしませんが、磁力での吸引や電波による発熱の危険があるため十分な注意が必要です。当院には、1.5Tと3.0Tの装置が導入されています。
特徴
- 他の検査より組織の描出の差を出すことに優れ、脳や軟部組織の検査に有用です。
- 任意にいろいろな断面を画像にすることが可能です。
- 撮像条件の設定でいろいろな画質を設定できます。
- 血流の画像や体内の水や脂肪を抑制・強調した画像を撮像できます。
核医学(RI)検査

核医学検査はRI検査とも呼ばれます。この検査は、放射性医薬品を体内に投与し、病気の診断を行う検査です。体内に集積した放射性医薬品から放出される放射線(ガンマ線)をガンマカメラで撮影し、画像化することにより体内の様子を調べます。この画像をシンチグラフィまたはシンチグラムといいます。
検査目的により、放射性医薬品の体内での分布の様子から、臓器の位置、形態、病巣の有無を調べたり、集積量の経時的な変化の情報を得たりして、病気の診断に役立てています。
放射性医薬品は、放射線を放出する性質を持った物質(ラジオアイソトープ:RI)を微量に含んだ医薬品であり、その種類によってある特定の臓器・組織に集まる性質を持っています。放射線を出す能力が時間とともに減少していく性質があります。体内に投与された薬は尿や便とともに排泄されたり、放射線の量が速やかに減少していくため、早いものでは数時間、遅くても数日でなくなります。
核医学検査の安全性:放射性医薬品は人体に直接働きかける効果・効能はなく、あくまで診断のための薬ですので副作用はほとんどありません。ごくまれに(検査10万件あたり1~2件)副作用の出現が報告されていますが、症状としては発疹、嘔気、皮膚発赤、悪心、顔面紅潮、掻痒感などで、軽微なものがほとんどです。また、被ばくについても核医学検査を受ける患者さんは、放射性医薬品を投与されますので、ある程度の放射線被ばくがあります。核医学検査1回あたりの被ばく量は、0.2~8ミリシーベルトで、エックス線検査と大きな違いはありません。当院では、放射性医薬品の患者さんへの投与量の記録、管理を行い、適切な投与量で検査を行っています。
当院で行っている主な検査:骨シンチ、心筋血流シンチ、脳血流シンチ、唾液腺シンチ、脳DATシンチ、心臓交感神経シンチ、腎シンチ
放射線治療
放射線治療は、外科手術、化学療法に並ぶがん治療の3本柱の一つであり、人体内のがんに対し、選択的に放射線を照射することで治療を行ないます。リニアック(LINAC)という治療装置を用います。制御された放射線を高精度で人体に照射して治療を行います。治療法としては、根治的放射線療法といって、がんを完全に治すことを目的として用いられる方法と、緩和的放射線療法といい、進行したがんの症状を和らげることにも用いられます。例えば、骨転移などの疼痛緩和で、生活の質(QOL)の向上に重要な役割を果たしています。また、緊急放射線療法で、急速に悪化する重篤な症状や生命に関わる危機を回避する為に行われる治療の対応も行っております。
治療の適応や治療期間は、放射線治療医が病状やご本人、ご家族や主治医の希望をお伺いしながら診察を行い決定していきます。
治療の目的には、根治的放射線療法・緩和的放射線療法・緊急放射線療法などを行っております。
認定資格等所得状況
| 種目 | 人数 |
|---|---|
| X線CT認定技師 | 3 |
| 救急撮影認定技師 | 2 |
| 検診マンモグララフィ撮影認定技師 | 1 |
| 放射線治療専門放射線技師 | 2 |
| 放射線治療品質管理士 | 3 |
| 医学物理士 | 2 |
| MRI専門技術者認定技師 | 1 |
| 超音波検査士(消化器) | 2 |
| 超音波検査士(泌尿器) | 1 |
| 超音波検査士(表在) | 2 |
| 医療情報認定技師 | 1 |